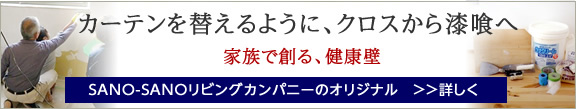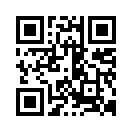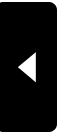2014年04月20日
『山月記』 再読
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県を拠点とする、工務店機能を備えた設計事務所です
「自分の家は自分でつくる」
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します
今日も1日、図面作成。
構造事務所への対応図面や申請関係など、描き進めています。
設計はいくら時間があっても足りないのが実感です。
それでもどこかで現場に入らなければならないので、時間のあるときに少しでも内容を詰めておきたいものです。

ちょっと休憩。
中島敦の『山月記』、再読。
この短編に凝縮された、なんとも苦い物語・・・。
李徴はなぜ、虎になってしまったのか??
「己の珠にあらざることを惧れるがゆえに、あえて刻苦して磨こうともせず、
己の珠なるべきを半ば信ずるがゆえに、碌々として瓦に伍することもできなかった」
・・・・・・
もう少し、図面描こう☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します
今日も1日、図面作成。
構造事務所への対応図面や申請関係など、描き進めています。
設計はいくら時間があっても足りないのが実感です。
それでもどこかで現場に入らなければならないので、時間のあるときに少しでも内容を詰めておきたいものです。
ちょっと休憩。
中島敦の『山月記』、再読。
この短編に凝縮された、なんとも苦い物語・・・。
李徴はなぜ、虎になってしまったのか??
「己の珠にあらざることを惧れるがゆえに、あえて刻苦して磨こうともせず、
己の珠なるべきを半ば信ずるがゆえに、碌々として瓦に伍することもできなかった」
・・・・・・
もう少し、図面描こう☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2014年01月01日
今年も宜しくお願い致します☆
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県中・東部を拠点とする、工務店機能を備えた設計事務所です。
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
新年、明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します!
一年の計は元旦にあり。
馬年…、ということもあり(?)、初心に戻って、じっくりと『竜馬がゆく』を再読しています。


青年の竜馬になりきって、気持ちが若返る感じです。
先ほど、竜馬が勝海舟の弟子になるくだりを読みました。
竜馬の生涯で後半にあたる年齢で、出会いがあったのですね…。
読書の愉しみを満喫しています。
ソフトバンクの孫さんに倣って、事務所の一角に写真を配置しました。

今年は、竣工する物件もあり、ひとつひとつカタチとして出来上がっていきます。
汗馬の労を厭わず、飛躍の年にしたいと思います☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
新年、明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します!
一年の計は元旦にあり。
馬年…、ということもあり(?)、初心に戻って、じっくりと『竜馬がゆく』を再読しています。
青年の竜馬になりきって、気持ちが若返る感じです。
先ほど、竜馬が勝海舟の弟子になるくだりを読みました。
竜馬の生涯で後半にあたる年齢で、出会いがあったのですね…。
読書の愉しみを満喫しています。
ソフトバンクの孫さんに倣って、事務所の一角に写真を配置しました。
今年は、竣工する物件もあり、ひとつひとつカタチとして出来上がっていきます。
汗馬の労を厭わず、飛躍の年にしたいと思います☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年11月15日
外山さんの本☆
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県東部、中部を拠点とする、工務店機能を備えた住宅設計事務所です。
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
外山 滋比古(とやま しげひこ)さんの『思考力』を読んでいます。

「大抵のことは知識で解決するが、よりよく生きるためには、生活と結びついた具体的な思考力を磨くこと」
知識のジレンマと限界を見据え、スポーツで身体を動かし、忘却、頭の掃除をし、直観的な思考力を磨く・・・。

内容は各センテンスに分かれてとても読みやすい。
「知識の罠」に、色々考えさせられます。
頭を柔らかくしたいです。
外山さんの本は、『思考の整理学』などが有名ですね。

アイデアの「発酵」、「触媒」、「寝かせる」など、刺激的な視点が面白い。
設計のエスキスにも、似たような感覚があります。
私の場合、読書は隙間の時間が集中できます。
一番良いのが、昼休みの、例えば料理を注文して、料理が出てくるまでの10~15分ぐらいが一番深く読み込めますね。
基本的に待つのが苦手なので、「積極的に待つ」姿勢をつくっていると落ち着きます。

今日は夕日が綺麗でした☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
外山 滋比古(とやま しげひこ)さんの『思考力』を読んでいます。
「大抵のことは知識で解決するが、よりよく生きるためには、生活と結びついた具体的な思考力を磨くこと」
知識のジレンマと限界を見据え、スポーツで身体を動かし、忘却、頭の掃除をし、直観的な思考力を磨く・・・。
内容は各センテンスに分かれてとても読みやすい。
「知識の罠」に、色々考えさせられます。
頭を柔らかくしたいです。
外山さんの本は、『思考の整理学』などが有名ですね。
アイデアの「発酵」、「触媒」、「寝かせる」など、刺激的な視点が面白い。
設計のエスキスにも、似たような感覚があります。
私の場合、読書は隙間の時間が集中できます。
一番良いのが、昼休みの、例えば料理を注文して、料理が出てくるまでの10~15分ぐらいが一番深く読み込めますね。
基本的に待つのが苦手なので、「積極的に待つ」姿勢をつくっていると落ち着きます。
今日は夕日が綺麗でした☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年10月14日
カミュ・著 『シーシュポスの神話』 再読
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県東部、中部を拠点とする、工務店機能を備えた住宅設計事務所です。
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。

シーシュポスは神々より、「巨岩を山頂まで押し上げ、その岩が自重で転がり落ちたのを、また麓から山頂まで運びあげる」という刑罰を課される。
そして、その作業は、延々と繰り替えされる。

日本の民話でいえば、「賽の河原」であり、無益で希望のない、まさに労働にあたります。
カミュは、シーシュポスがこの作業に意識的に目覚めていることを、悲劇的であると記しています。
と同時に、「頂上を目がける闘争」ただそれだけで、人間の心をみたすのに十分足り得る、シーシュポスは幸福なのだ…、とも。

この本を改めて手に取ったのは、日々の私達の日常も、多かれ少なかれ似たところがあると思うからです。
「不条理な人間は、自分こそが自分の日々を支配するものだと知っている。
人間が自分の生へと振り向くこの微妙な瞬間に、シーシュポスは、自分の岩のほうへと戻りながら、あの相互につながりのない一連の行動が、かれ自身の運命にあるのを、かれによって創りだされ、かれの記憶のまなざしのもとにひとつに結びつき、やがては彼の死によって封印されるであろう運命と変わるのを凝視しているのだ。」
秋の夜長、こんなことも考えてしまいます☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。

シーシュポスは神々より、「巨岩を山頂まで押し上げ、その岩が自重で転がり落ちたのを、また麓から山頂まで運びあげる」という刑罰を課される。
そして、その作業は、延々と繰り替えされる。

日本の民話でいえば、「賽の河原」であり、無益で希望のない、まさに労働にあたります。
カミュは、シーシュポスがこの作業に意識的に目覚めていることを、悲劇的であると記しています。
と同時に、「頂上を目がける闘争」ただそれだけで、人間の心をみたすのに十分足り得る、シーシュポスは幸福なのだ…、とも。
この本を改めて手に取ったのは、日々の私達の日常も、多かれ少なかれ似たところがあると思うからです。
「不条理な人間は、自分こそが自分の日々を支配するものだと知っている。
人間が自分の生へと振り向くこの微妙な瞬間に、シーシュポスは、自分の岩のほうへと戻りながら、あの相互につながりのない一連の行動が、かれ自身の運命にあるのを、かれによって創りだされ、かれの記憶のまなざしのもとにひとつに結びつき、やがては彼の死によって封印されるであろう運命と変わるのを凝視しているのだ。」
秋の夜長、こんなことも考えてしまいます☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年10月06日
歯ごたえがあります☆
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県東部、中部、富士、富士宮を拠点とする、工務店機能を備えた注文住宅をつくる設計事務所です。
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
建築家・内藤廣さんの東京大学での講義本、3部作。

「構造デザイン講義」、「環境デザイン講義」に続いて、最後の「形態デザイン講義」。
細切れの時間を使って読んでいます。
今回も、内容が充実しています。
考え方が大人。
私のバイブル本。
1歩でも近づきたい☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
建築家・内藤廣さんの東京大学での講義本、3部作。
「構造デザイン講義」、「環境デザイン講義」に続いて、最後の「形態デザイン講義」。
細切れの時間を使って読んでいます。
今回も、内容が充実しています。
考え方が大人。
私のバイブル本。
1歩でも近づきたい☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年10月03日
面白い~♪
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県東部、中部、富士、富士宮を拠点とする、工務店機能を備えた注文住宅をつくる設計事務所です。
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
昼休みに読書中☆

『看板のない居酒屋』 岡村佳明・著(岡むら浪漫 代表)
あんまりお酒飲めないですが、こういうお店なら行ってみたい!
生きていく上でのエッセンスが入ってます☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
昼休みに読書中☆
『看板のない居酒屋』 岡村佳明・著(岡むら浪漫 代表)
あんまりお酒飲めないですが、こういうお店なら行ってみたい!
生きていく上でのエッセンスが入ってます☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年09月22日
幸田露伴・著 『五重塔』 再読
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県東部、中部を拠点とする、工務店機能を備えた住宅設計事務所です。
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
『五重塔』を、7年ぶりに再読しました。

読み始めは、やっぱりというか、文語体の表現にとっつきにくさを感じつつ読み進めていくと…。
主人公の大工、のっそり十兵衛が、寺の上人様に五重塔を建てさせて欲しいと哀訴、師匠である川越源太との押し問答と決着…、次第に読み慣れ、物語に惹き込まれていきます。
そして、十兵衛の現場作業、受難、塔の完成、嵐のクライマックスへと、めくるめく話は展開していきます。
特に興味深いのが、十兵衛が傷を負った次の日でも、休まずに現場に行く場面。
十兵衛は日ごろ、「のっそり」と職人に陰口を言われつつも、現場をなんとか指揮している。
傷負いても、あえて仕事に出る姿勢によって、荒くれ職人連中をまとめ、現場を鼓舞し、塔の完成に漕ぎつける。
十兵衛は、自分が職人達にどう見られているか、その機微をよく理解していた。
この雰囲気は、私も体験的によく知っています。
最後は理屈ではない事が、あったりするのです。

わずか100ページの小説ですが、露伴の渾身の名作だと思います☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分でつくる」。
セルフビルドによる、参加型家づくりを提案します。
『五重塔』を、7年ぶりに再読しました。

読み始めは、やっぱりというか、文語体の表現にとっつきにくさを感じつつ読み進めていくと…。
主人公の大工、のっそり十兵衛が、寺の上人様に五重塔を建てさせて欲しいと哀訴、師匠である川越源太との押し問答と決着…、次第に読み慣れ、物語に惹き込まれていきます。
そして、十兵衛の現場作業、受難、塔の完成、嵐のクライマックスへと、めくるめく話は展開していきます。
特に興味深いのが、十兵衛が傷を負った次の日でも、休まずに現場に行く場面。
十兵衛は日ごろ、「のっそり」と職人に陰口を言われつつも、現場をなんとか指揮している。
傷負いても、あえて仕事に出る姿勢によって、荒くれ職人連中をまとめ、現場を鼓舞し、塔の完成に漕ぎつける。
十兵衛は、自分が職人達にどう見られているか、その機微をよく理解していた。
この雰囲気は、私も体験的によく知っています。
最後は理屈ではない事が、あったりするのです。

わずか100ページの小説ですが、露伴の渾身の名作だと思います☆
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年07月16日
『Dr.NOGUCHI』 大人読み
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県東部、中部、富士、富士宮を拠点とする、工務店機能を備えた注文住宅を造る設計事務所です。
「自分の家は自分で造る」。
セルフビルドによる、参加型家造りを提案します。
やってしまいました。
ついつい、手にした1冊をパラリとめくった後は、もう止まらない。
『Dr.NOGUCHI』、全17巻、4時間半で一気に読破。
気づいた頃には、24時過ぎ。
いや~、改めて読み返しても面白いですね。

特に、作品中盤から、ノグチが渡米し、ペンシルバニア大学で蛇毒の研究、梅毒のスピロヘーターの発見、ロックフェラー研究所へ入所、黄熱病との闘いと、ストリーがめまぐるしく展開し、内容にグイグイ引っ張られていきます。
ノグチは人との出会いを掴み取る天才ですね。
小林栄先生、北里柴三郎博士、フレクスナー教授、製薬王・星一、石油王・ロックフェラー、はたまたフォードやエジソンまで、ノグチのバイタリティーに共鳴するかのように引き寄せられてきます。
また、むつ利之さんのねばりのある筆致は、この作品を良くひきたて、ノグチを魅力的に描ききっています。

↑同郷同士、星一(左)と野口英世(右)のスナップ。
好きな写真です。
多少の後ろめたさを感じながら、「昨日も働いたし、祝日の夜だからまぁ良いか」と、自分を納得させ、寝ようと思います。
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分で造る」。
セルフビルドによる、参加型家造りを提案します。
やってしまいました。
ついつい、手にした1冊をパラリとめくった後は、もう止まらない。
『Dr.NOGUCHI』、全17巻、4時間半で一気に読破。
気づいた頃には、24時過ぎ。
いや~、改めて読み返しても面白いですね。
特に、作品中盤から、ノグチが渡米し、ペンシルバニア大学で蛇毒の研究、梅毒のスピロヘーターの発見、ロックフェラー研究所へ入所、黄熱病との闘いと、ストリーがめまぐるしく展開し、内容にグイグイ引っ張られていきます。
ノグチは人との出会いを掴み取る天才ですね。
小林栄先生、北里柴三郎博士、フレクスナー教授、製薬王・星一、石油王・ロックフェラー、はたまたフォードやエジソンまで、ノグチのバイタリティーに共鳴するかのように引き寄せられてきます。
また、むつ利之さんのねばりのある筆致は、この作品を良くひきたて、ノグチを魅力的に描ききっています。

↑同郷同士、星一(左)と野口英世(右)のスナップ。
好きな写真です。
多少の後ろめたさを感じながら、「昨日も働いたし、祝日の夜だからまぁ良いか」と、自分を納得させ、寝ようと思います。
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村
2013年06月30日
『粗い石』 再読
SANO-SANOリビングカンパニーは 静岡県富士宮市にある工務店機能を兼ね備えた注文住宅を造る建築設計事務所です。
「自分の家は自分で造る」。
セルフビルドによる、参加型家造りを提案します。
時々、読み返す本があります。
F・プイヨンの『粗い石』は、その1冊です。

舞台は、中世のフランス。
物語は、命がけで修道院の再建に取り組んだ、修道士の生涯を描いたもの。
この時代、修道士は設計者であり現場監督の立場にあたります。
正直、読み通すまでに、2回ぐらい挫折しています。
しかも、本を買ってから5~6年かかって。
2年ぐらい前に、意を決して再挑戦し、力ずくで読破しました。

前半は話に入り込めず、退屈な内容(?)に苦痛を覚えつつ、分からない部分は飛ばしながら読み進めると・・・。
中盤の、主人公のギヨームが設計に苦悶する辺りから、石切り場での職人との格闘、コストや工期の問題、教会上層部との衝突、だんだんと物語に惹き込まれていきます。
そして傷を負ったギヨームの苦悩と、責任感に突き動かされ嵐の中に飛び込む終盤へと、物語は加速していきます。
修道士達は、修道院再建に必要な巨石を採掘し、運ぶ道を舗装することから手をつけます。
気の遠くなるような労力と時間、人間臭い様々な雑事を積み重ねて。
そして、トラブルを1つ1つ乗り越えていきます。
「あるときは理性が勝ち、あるときは感じや図面の正しさが勝つ。
幾何学と象徴が拮抗し、決まる形は双方の綜合となる。
この瞬間は、重大だが軽やかだ。」
建築を造るとは、本当はこういうことだったのだ・・・。
読み返すたびに、冷や水を浴びせられる感じがします。

私はモデルとなったル・トロネ修道院を、未だ訪れていません。
しかし、将来の訪問を、今から楽しみに想像しています。
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.

にほんブログ村
「自分の家は自分で造る」。
セルフビルドによる、参加型家造りを提案します。
時々、読み返す本があります。
F・プイヨンの『粗い石』は、その1冊です。
舞台は、中世のフランス。
物語は、命がけで修道院の再建に取り組んだ、修道士の生涯を描いたもの。
この時代、修道士は設計者であり現場監督の立場にあたります。
正直、読み通すまでに、2回ぐらい挫折しています。
しかも、本を買ってから5~6年かかって。
2年ぐらい前に、意を決して再挑戦し、力ずくで読破しました。
前半は話に入り込めず、退屈な内容(?)に苦痛を覚えつつ、分からない部分は飛ばしながら読み進めると・・・。
中盤の、主人公のギヨームが設計に苦悶する辺りから、石切り場での職人との格闘、コストや工期の問題、教会上層部との衝突、だんだんと物語に惹き込まれていきます。
そして傷を負ったギヨームの苦悩と、責任感に突き動かされ嵐の中に飛び込む終盤へと、物語は加速していきます。
修道士達は、修道院再建に必要な巨石を採掘し、運ぶ道を舗装することから手をつけます。
気の遠くなるような労力と時間、人間臭い様々な雑事を積み重ねて。
そして、トラブルを1つ1つ乗り越えていきます。
「あるときは理性が勝ち、あるときは感じや図面の正しさが勝つ。
幾何学と象徴が拮抗し、決まる形は双方の綜合となる。
この瞬間は、重大だが軽やかだ。」
建築を造るとは、本当はこういうことだったのだ・・・。
読み返すたびに、冷や水を浴びせられる感じがします。

私はモデルとなったル・トロネ修道院を、未だ訪れていません。
しかし、将来の訪問を、今から楽しみに想像しています。
セルフビルドな家づくり☆ sano-sanoリビングカンパニーのH.P.
にほんブログ村